先人たちが、いつから「色」を感じとり、それを「色」として認識しだしたのか?
古代人たちは、日々の生活の中で太陽が天空に輝く喜びと、真っ暗な闇の夜の恐れに色彩を感じていたと思われます。色のルーツは「光」から派生し、「明・暗・顕・漠」と表現され、「明」はアカで夜明けとともに空が赤くなっていく様を、「暗」のクロは太陽が沈んでしまった状態、「顕」はシロで夜が明け辺りがはっきり見える様子、「漠」はアオで明と暗の中間の青みがかった空を表していて、これらの4原色を純粋色彩語とし現代では「赤・黒・青・白」とされます。
ただし古代社会にこの4色しかなかったわけではなく、ほかに「クレナイ」「アカネ」「ミドリ」「ムラサキ」「タン」「シラニ」などの表現もありました。これらは植物や鉱物などの具体名から生まれ、海や山、空、雪、雨、水など自然そのものの表現に代用されていました。概念として「黄」は存在せず、色名として認識されるようになったのは6世紀頃、中国から「陰陽五行説」が伝わってからのことです。
この明暗顕漠の「明と暗」アカとクロ、「顕と漠」のシロとアオの2項対立の概念が生まれ、日本の独特の配色観のひとつとなったわけです。木は「木霊」が宿る神であるように、日本人は古来から自然崇拝(アニミズム)によって自然そのものを神体として崇めてきたため、植物由来の色名の中に自然信仰を巧みに織り込み愛でていたといわれます。
こうした自然の色への畏敬の念は、平安の女房装束の「襲の色目」によく表現されています。宮中の女性たちにとって「時に合いたる」、つまり季節に合った装いをすることは、自らのアイデンティティや知性、教養を表現し、自然への感謝と畏敬を表す「心ある」手段であり、自然と同化することに他ならなかったのです。日本の伝統色には数多くの美しい色がありますが、それはまた次回にご案内いたしましょう。










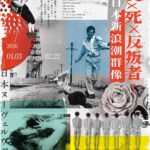

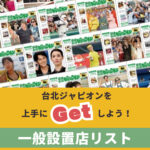






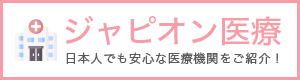
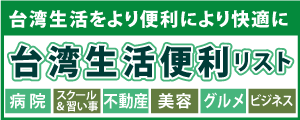






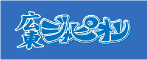



 PAGE TOP
PAGE TOP